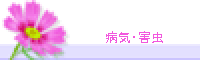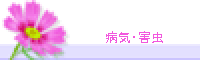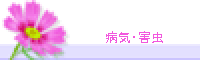
観葉植物は比較的病気や害虫が少ない植物であり、それ以外の要因で上手く生育しない場合も多い。根詰まりによる生育不良、肥料不足、湿度不足、光線の強弱などの要因も考慮する必要がある。
置き場の環境を清潔に保つことに加えて、植物体そのものも花がらや枯れ葉を放置せず、こまめに取り除いて清潔にする。培養土の再利用も避けたほうがよい。
害虫
カイガラムシ…白い綿状、茶褐色の1枚貝状(体長1〜5mm)
葉の表や裏、茎や幹につき、動かないで増える。高温乾燥で発生しやすい。
生育不良。水飴状の排泄物が茎葉につき、べたべたする。すすをぬったように黒く汚れるすす病となる。
アブラムシ…緑、褐色、黒などの体色(体長約3mm)
主に成長部付近の茎葉やつぼみに集団発生する。
植物の液汁を吸い、生育不良を起こすウィルス病を感染させる。すすをぬったように黒く汚れるすす病となる。
ダニ類…体色は白または赤
葉茎やつぼみ。注意してみないとわからない。高温多湿で発生しやすい。
植物の液汁を吸い、葉色を不良にする。生育不良。多発するとクモの巣状に糸を引く。
オンシツコナジラミ…乳白色の有羽根害虫(体長3〜4mm)
葉の裏につくので目につきにくいが、葉に触れると粉が飛ぶように、一斉に飛び立つ。
植物の液汁を吸い、生育を不良にする。多発するとクモの巣状の糸を引く。
ナメクジ…薄い茶褐色の軟体動物(体長3〜4cm)
夜に活動し、未展開の若い葉やつぼみをかじる。
葉や花に穴をあける。
病気
炭疽病…葉の表面に円形、楕円形などのやや大きな病斑ができ、その部分が枯れる
15〜20度、多湿でで発生。初夏と秋に多い。
ゴムの木類、ドラセナ類、サボテン、クロトン、ペペロミア、アナナス類など。
斑点病…葉の表面に斑点状の病斑がつく
多湿で発生。
シュロチク、ヤシ類、クロトン、モンステラなど。
灰色カビ病…主に成長部の葉茎、つぼみ、花に灰をふりかけたようなカビが発生し、僅かな風でも飛散する
15〜20度、多湿で発生。春や秋に発生しやすい。
ベゴニア類など。
うどんこ病…主に葉が、うどんこをふりかけたように白くなる
25度、多湿で発生。初夏、初秋に発生が多い。
ベゴニア類など。
疫病…葉や葉柄に水浸状の病斑が広がり枯れる
多湿や水のやりすぎで発生。
アフェランドラ、ドラセナ、コルジリネなど。
軟腐病…地際部や土中の茎や根が油浸状に腐り、腐汁は悪臭を放つ
水のやりすぎや土壌の病菌で発生。
多肉植物、サンセベリア、アロエなど。
白絹病…地際部の葉茎に白い絹糸状の菌糸が発生、軟化腐敗が始まり、枯れる
土から感染。高温多湿期。水のやりすぎで発生。
ディジゴセカ、ドラセナ類など。